
1912年イギリスの豪華客船タイタニック号沈没をきっかけに遭難や安全に対して通信システムの見直しがされましたが、それでも次のような問題点がありました。
通信システムの概念図としては次の通りです。(国土交通省からの引用です。)
図1. 概念図

衛星通信がないGMDSS移行前のシステムでは、遭難した場合は付近の船舶局へモールス信号で遭難信号を送り、それを順次中継していくシステムでした。 これは信号が届く範囲に船舶が航行していないと通信が途切れてしまう可能性も考えられます。それに対してインマルサット(INMARSAT)衛星を中継すれば確実に陸上無線局へ遭難信号が伝わり、 救助活動が行われるシステムとなっています。衛星EPIRBについてもコスパス・サーサット衛星を中継して陸上無線局に遭難信号が伝わります。 GMDSS移行前のシステムでは衛星EPIRBに類似した機能は遭難信号自動発信機で、海岸局の付近でしか機能が保証されない限定されたものだったようです。
GMDSSの水域
INMARSAT衛星を中継することで洋上通信のカバレッジが格段に広がりました。海岸局から電波が到達しない場所でもINMARSAT衛星がカバーするし、 INMARSATがカバーしていない海域であってもMF帯の電波で海岸局と通信する手段をとることで、理論的には地球上の全ての海域で船舶局と海岸局が直接通信できるようになりました。 GMDSSでは、(1)VHF帯で海岸局と通信可能な海域をA1水域、(2)MF帯で海岸局と通信可能な海域をA2水域、(3)INMARSATで海岸局と通信可能な海域A3水域とし、 A1,A2,A3以外の海域をA4水域とし、それぞれの海域を航行するために装備すべき無線機器を定義しています。A1,A2海域を航行する船舶であればINMARSATは不要ですが、 INMARSATがあればA3海域内ではVHF無線設備やMF無線設備がなくとも海岸局と直接通信ができるため、HF無線設備(VHFとMFの中間周波数帯を使用)の代りにINMARSATを使う等、 選択・代替することができます。実際に装備する設備については、船種、総トン数の違いを考慮した上でSOLAS条約や船級等で詳細が規定されていますが、 おおむねの考え方をまとめると表の通り(少し大きいので別窓で開くとよい)になります。
また水域のイメージは次の図の通りになります。(日本財団図書館からの引用)
図2. A1,A2,A3水域のイメージ

図3. A3海域(INMARSATのカバレッジ)
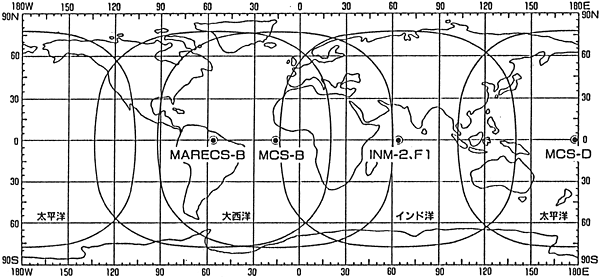
A1,A2水域は海岸局の設置状況によるため、各国ごとに設定されます。日本はA1水域は設定されておらず、A2水域は次の図の通りとなります。
図4. 日本のA2水域
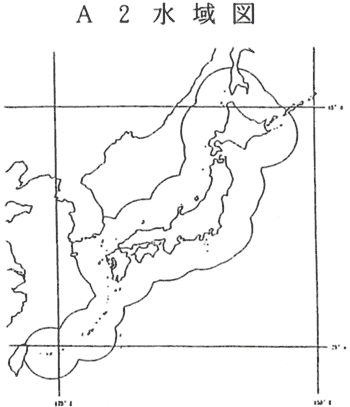
GMDSS統合システム
無線電話や直接印刷電信の設備のほかに航行の安全確保のためにECDISやBNWASといった機器の装備が義務付けられる船舶があります。 ECDISは電子海図情報表示装置で紙の海図の替りにコンピュータのディスプレイに電子海図を表示する装置で、 BNWASは俗にいう居眠り防止装置です。これらの装置は今までのGMDSS機器とインターフェースをもち、 データや信号のやり取りを行いながら稼働します。いわばGMDSSを統合したシステムです。
船舶の安全な航行のためにGMDSSでは様々な機器が定義されています。 航行する水域、船種・用途、船籍、総トン数等や船舶の運航方式を定めた上で、 条約や船級の規定にもとづいてチェックを行いながら、船舶局の無線通信システムの設計が行われます。